「英語で“ビッグ・ジョン”、そういう意味だよ」
“なぞの巨人”が淡々とそう説明する。

CD(『Misturada』)のブックレット用にと、参加者のコメントどりをしながら最後の番となった“ビッグ・ジョン”ことジョルジョアン。表情はまだ硬い。だが、つぎに発したことばが好奇心の導火線となる。
「バンダ・ブラック・リオというグループにいたんだよ。70年代の話になるけど……」
“ブラジルのアース・ウィンド&ファイアー”との異名をとるバンダ・ブラック・リオ(BBR)。この名前が出てくるなり、膝から崩れおちそうになった。ボサノヴァ、サンバ、あるいはMPBでもいい、正統派のブラジル音楽以外の文献がほぼ皆無だった時代、喉から手が出るほど欲していたことばが当事者から発せられようとは。リオの、ブラジルのファンク・シーンを牽引していた歴史の生き証人がいきなり目のまえに現れたのだから、興奮を抑えろというほうがムリだろう。
“そうか、そうだったのか”……彼の素顔を事前に知らなかったことがとても悔やまれる。正直なところ、CDの中で彼の立場はめぐまれているとは言えなかった。ジョルジョアンの個性である、まろやかな声質が生かされているとはいえ、凡庸なポップスとして無難に着地しているきらいがある。彼の性格からしてBBRの再現みたいなものをみずから進んでやるようなこともないだろうが、CDのコンセプトにもっと近づける方法はあったはず。当時の話を聞けば聞くほどそういうのが見えてきた。
ブラック・リオの伝説
要約するとこうなる。ジョルジョアンが加入したのは2枚めのアルバム『Gafieira Universal』(1978年)からで、キーボードを中心に作詞作曲、歌までなんでもこなした。メンバーの中で最年少だったが、重要なポジショニングを任せられる。それが証拠にバンドはインスト系としてデビューしながらも、彼の参加を機に大幅なヴォーカル・パートが設けられるからだ。有名無名問わず多くの同類が当時いたが、折り紙つきの実力はミュージシャン仲間からも一目置かれるほどだった。同時期、ジルベルト・ジルがリリースした『Realce』(1979年)など、ジルにとってかつてないほどアーバン色が濃厚になるが、これもBBRの影響があるだろうとジョルジョアンは話す。
1980年のサードアルバム『Saci Pererê』をもって解散(2000年以降メンバーの子息を中心に再結成)。やがてジョルジョアンは、ブラジル音楽の深部へとさらに吸い寄せられるようにコンテンポラリーなサンバ・バンド、バタコトに合流する。
BBRが解散した背景にはもうひとつ大事な理由、バイレ(パーティ)・シーンとの深い関わりがあった。アメリカのブラック・シーンに共鳴しながら70年代前半からディスコの箱バンとしてスタート。ジェイムス・ブラウンやルーファス・トーマスといったファンクマスターの定番を中心に生演奏していたものの、ダンスをするための音楽がDJのまわすレコードに取って代わることで、箱バンとしての役目に終止符が打たれる。ブラジルでも時代の変遷に逆らえなかったわけだが、こうした営業的な活動をしながらも、いっぽうではファンクのリズムにサンバを和合することでオリジナルなグルーヴを編み出していたことは特筆に値する。BBRがジョルジョアンを迎えたときのアルバム名“Gafieira Universal”(ガフィエイラ=ダンスホール)が意味するものも、きっとそうしたことと無縁ではない。
おもいがけない出会いにより最後まで気が抜けないなか、うしろ髪を引かれるおもいでメネスカルのスタジオをあとにする。しかしこの時点で、なお帰国日までまるまる一週間あった。初日のトラブルをのぞけば、そのあとの作業はおもいのほか暇どらなかったのである。
“さて、残りをどうやって過ごそうか”ーーそんな軽い気持ちをコーディネーターのあるひと言が吹き飛ばす。“仕事が終わったんだから帰るよ。サンパウロ(自宅)で待ってるカミさんの顔を早く見たいんだ”。彼の家に泊まらせてもらうこともかんがえてはみたが、ここはひとつおおきな賭けにでることを決意。リオ沿岸の町マカエまで向かうことに。そこには数年まえから文通していたペンパルが暮らしていた。いまでいうメル友。顔はもちろん、くわしい素性をまったく知らない。
音の旅はつづく
リオの中央駅から北東に伸びる長距離バス、といっても半世紀は酷使されてきたようなオンボロのマイクロバスにゆられること三時間。黒人で満席の中にひとりのアジア人。冷たい視線が容赦ない。冷房などあるわけなく、窓は全開。外からのチリやホコリ、前席でこどもが食べているスナック菓子など、いろんなものが顔に飛んでくる。舗装されていない車道はトランポリンの上を走行しているかのようで、バスを上下に激しく揺らす。緊張しっぱなしで酔うことはなかったが、寝たら最後だとおもい、荷物は身体と密着させ抱えこむように守った。がまんの限界をなんどか経験すると、西日に覆われた窓の景色にようやく目的地の町並みが映る。揺れがおさまりエンジン音が車体に吸収された瞬間、風船がしぼむように全身のチカラが抜け、おもわず笑みがこぼれてしまった。
とつぜんの訪問にもかかわらず、ペンパルの家族が自宅の玄関でにこやかに待つ。海沿いの小さな町。カーニバル時期と重なったため、ほとんどの商店がシャッターを降ろしていたが、住宅街にまわると所々で好き勝手に騒ぐ集団が視界に入る。

近所の家でやっていた音楽パーティ
浅草サンバカーニバルの何百倍もの規模を想像していただけに、これにはちょっと拍子抜けしてしまったものの、これはこれで味わい深い。“いいおもいでになりそうだ”ーーそうつぶやくのもつかの間、耳を疑うようなことばがペンパルから発せられるーー“エグベルト・ジスモンチといっしょに活動していたミュージシャンが近所にいるから紹介するよ。名前はピリ・ヘイス”。
“えっ!ピリってあの!?”ーー奇跡のブラジル、その奥義をおもい知らされる。こうなるとメネスカルのスタジオにいたことさえ遠いできごとだ。ここでもほっぺをつねってみる。もちろん痛くない。さらに、上気した顔に上書きされるように一枚の絵が浮かんできた。それは幻のデビューアルバムと呼ばれていたピリの『Voces Querem Mate?』(1970年)。“あわよくば……”との淡い期待に胸をふくらませながら通訳なしで本人と向きあう。不自由な語彙力はともかく、熱意だけでも伝わってくれたらいいのだが……。

日本から来たとつぜんの訪問者にピリも内心とまどっていただろうに、しかしある意味わたしの気持ちだってそれと変わリない。最新作だという『Coisa Rara』(1991年)をいただき、おいとまする。

ペンパルの友人がやっていたバンドの練習風景。すでにマッキントッシュを使っていたのでびっくり
人生において輝ける時間は決められている。すべての運が払底してしまったかのような怒涛の体験が最後の最後までつづいたブラジルの旅。恥ずかしいことに鈍感な若者にしかできない、そんな甘酸っぱい記憶がなつかしい。
SHARE
Written by

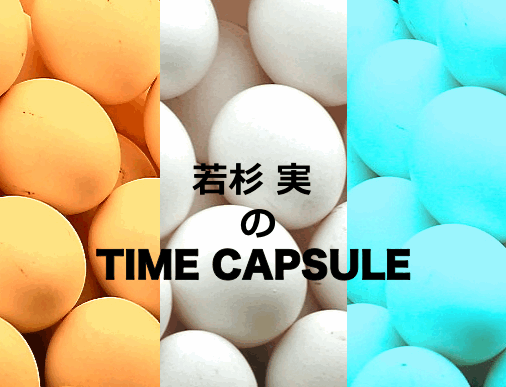
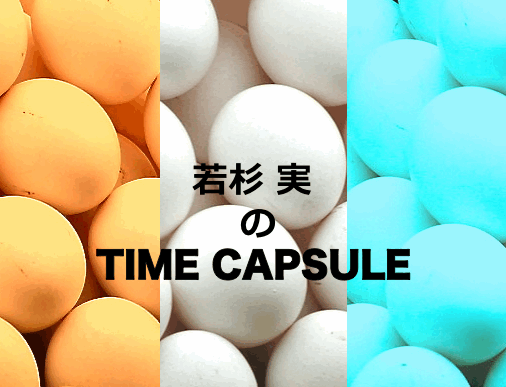
 若杉 実
若杉 実 