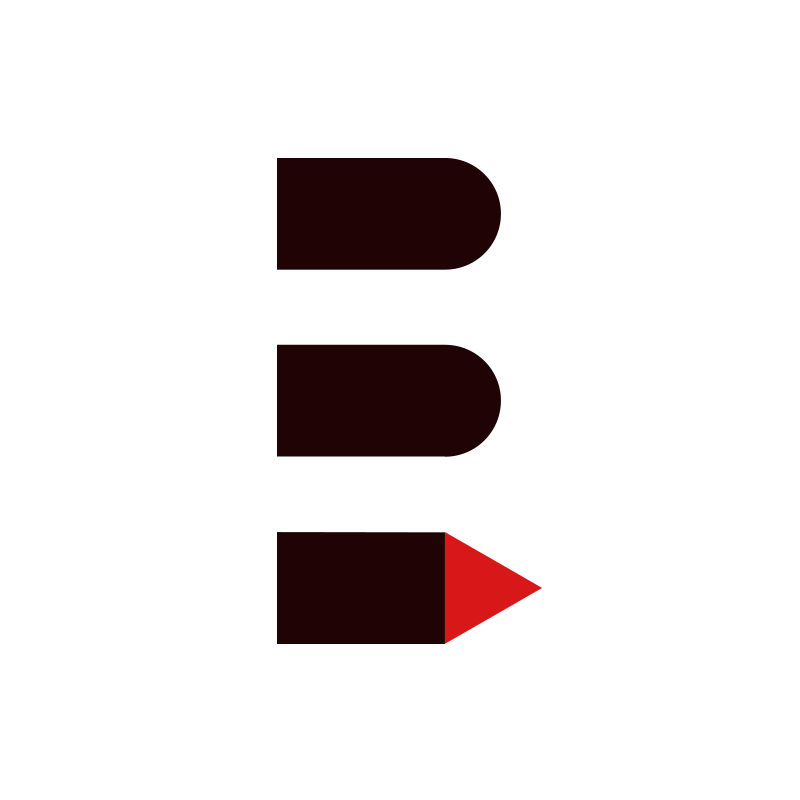もっと知りたい細野晴臣(後編)
2019年、音楽活動50周年を迎えた細野晴臣さん。「50年」音楽活動を続けているってよくよく考えなくてもものすごい事なんだけど、さらに細野晴臣さんがシーンに与えた影響は計り知れず。はっぴいえんど、YMO、ロック、テクノ、エレクトロニカ、映画、プロデュース、シンガーソングライター…「細野晴臣とは?」を考えた時、ちょっとやそっとじゃ説明できません。引き出しが多いとか懐が深いとか、そんな生易しいもんじゃない。もはや「細野晴臣という宇宙でありひとつの文化」だよね…。 そんな思いを元に考えた企画が『細野晴臣のABC』。細野晴臣という宇宙をAから順に読み解いていくことで、「細野晴臣辞典」を作ってしまおうという試みです。執筆者としてお迎えしたのは音楽ライターの森朋之さん。ここ数年にわたり継続的に細野さんにインタビューしている方です。森さんの視点で紡がれる細野晴臣入門、保存版です。
Text:TOMOYUKI MORI
Edit:ADO ISHINO(E inc.)
■前編はこちらから■
【N】ノンスタンダード・レーベル(YMO散開後に細野さんが立ち上げたレーベル)
YMO散開(ちなみに“散開”とは“兵が間隔をおいて散らばり、展開する”という意味の軍事用語です)の翌年、1984年に細野さんレーベル「ノンスタンダード」を立ち上げます。このユニットからは、細野さん自身のユニット“フレンズ・オブ・アース”、鈴木惣一朗率いる“ワールドスタンダード”、さらに“ピチカート・ファイヴ”などが作品を発表。80年代中頃の音楽シーンのなかで、“多くの人々に支持されながらも、作り手側の感覚が標準化されていない音楽”を目指したノンスタンダードはわずか3年ほどで終わってしまいますが、“渋谷系”をはじめとする90年代以降のJ-POPシーンに大きな影響を与えています。
2019年3月には、鈴木惣一朗さんが監修したCD4枚組「NON-STANDARD collection-ノンスタンダードの響き』がリリースされました。細野さんの名盤「S-F-X」に収録されなかった「あくまのはつめい」「北極」、ピチカート・ファイヴのデモ音源3曲など、貴重なトラックも収録。新しいポップスの在り方を目指したノンスタンダード関連の作品は、いま聴いてもまったく古びていない…というより、2020年代を目前にした現在にこそフィットしていると思います。
■参照記事■
NON-STANDARD collection -ノンスタンダードの響き-

NON-STANDARD collection-ノンスタンダードの響き(出典)
【O】お笑い
1980年前半、お笑いブームを巻き起こした伝説的番組「THE MANZAI」。ツービート、島田紳助・松本竜介、B&B、ザ・ぼんちなどのスターを生み出したこの番組に、YMOが出演したことがあります(1982年3月30日放送)。芸名(?)は、トリオ・ザ・テクノ。坂本さん、高橋さん、細野さんが物まねを披露するコント(細野さんは林家三平師匠のマネをしてました)は普通におもしろく、得体の知れない衝撃をお茶の間に与えました(たぶん)。楽曲とコントで構成された「増殖-X∞Multiplies」(1980年)をリリースしたこともある3人なので、もともとお笑いに興味を持っていたのだと思いますが、当時の映像を見ると“ここまでやるか?!”というハッチャケぶりです。
細野さんのお笑い好きはいまも健在。2017年11月に行われた東京・中野サンプラザ公演には、ナイツ、清水ミチコ・イチロウが出演。ナイツは細野さんのキャリアをテーマにしたネタを披露し、会場を沸かせました。ナイツの塙宣之さんは「“ヤホー漫才”は細野さんの影響から生まれた」と公言しているほどの細野ファン。細野さんの存在はミュージシャンのみならず、お笑いにも大きな影響を与えているようです(ほんとです)。
【P】プロデュース
キャラメル・ママ(後のティン・パン・アレー)のメンバーとして、荒井由実「ひこうき雲」「MISSLIM」、小坂忠「ほうろう(HORO)」、吉田美奈子「扉の冬」、矢野顕子「JAPANESE GIRL」などのプロデュース、演奏に関わってきた細野さんは、その後も幅広いアーティストの作品をプロデュースしています。もっとも有名なのはシーナ&ザ・ロケッツの2ndアルバム「真空パック」(1979年)でしょうか。代表曲「YOU MAY DREAM」を収めた本作は、当時の最先端だったニューウェイブ、ポストパンクのテイストをいち早く取り入れ、オーソドックスなロックンロールを見事にアップデートさせた作品です。(ちなみにシナロケのギタリスト、鮎川誠さんはYMOの「ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー」の「Day tripper」(ザ・ビートルズのカバー)でもギターを弾いています。個人的に心に残っているのは、80年代に活動した“ゲルニカ”の「改造への躍動」(1982年)。戸川純さんの個性的なボーカルと戦前の日本的なムード、近未来的な世界観がひとつになったこのアルバムは日本のオルタナティブの先駆者的な作品であり、プロデューサーとしての代表作だと断言します!
SHARE
Written by