文化都市ボローニャ
“ふるさとに似ている……”ーーボローニャ駅に降り立つとデジャヴのような感覚に襲われた。街の歴史が古く、潮のにおいがしない代わりに乾燥した木の香りが鼻孔をくすぐる。旧市街地にあるボローニャ大学は西欧最古の大学らしい。わたしの田舎にも日本最古の学校があった。
“カンカンカン”ーー日が沈みかけたころ、街を鎮めるように教会の鐘が遠くで鳴った。屋根は赤煉瓦で統一されていて、そこに薄陽が降りるときれいなグラデーションが波打つように浮かぶ。石畳の歩道からは古代都市の音が聞こえてきそうだ。そこに日本からの旅人の足音がパタッ、パタッと折り重なる。

宿の屋上から
足は市街地中央にあるマッジョーレ広場の前で止まった。そこに広がるのは時間までもが止まったかのような空間。こちらを見下ろすように、重厚かつ威厳に満ちた石造建物の数々が並ぶ。
到着したのが日曜だったため店はほとんど閉まっていたが、代わりにこの広場ではお祭りのようなものがおこなわれていた。中央にはステージがあり、大きなスピーカーからは激しいギターの音が流れ、建物にそれが反射し倍になって拡散される。若者は群がり、年配者は離れた場所で友人や恋人や家族とともに語らい安息日の夜を楽しむ。ただそれだけの光景にほのかな興奮を覚える。これからの数日間、どんなことを期待し幸せでいられるのか、自分の気持ちが高揚しているのがわかった。
つぎの日、さっそく目的を果たすため、ある店に向かう。“ここらへんでいいのかな”ーー地図を開き、印をしておいた場所に指をさす。教会から北に向かうこと30分。地球の歩き方で予習していたポルタ・ラメ史跡、博物館や映画館が近接する一画に、〈クアドロフェニア〉と書かれたレコード屋の看板を発見する。モッズのバイブル(映画)とおなじ名前。この時点で映画は観ていない。モッズ世代ではないから、というのは言い訳だろう。“日本に帰ったら急いでビデオを借りよう”ーーそんな思いも、ものの数分もしないうちに消えてなくなるくらい、濃密な時間が迫っていようとは。
伊ジャズ・ピアニストの雄とご対面
“こんにちは。日本から来ました……”ーーあとは英単語を適当に並べながら説明に入る。この店のことはマンハッタンレコードを通じて知っていた。わたしが企画した〈ニュー・バランソ〉の序章となるマンドレイクの再発を、会社を通じて提案してくれたのがここのオーナーだったからだ。それなら話は早いと、親身になって応対していただく。ここで、例のイタリア人ピアニストのことを切り出してみることに。
「数ヶ月前マルコ・ディ・マルコさんに電話取材したんです。彼はボローニャに住んでいるはずですが、ご存じですか?」

ふたりの店員はいったん顔を見合わせると、もういちどこちらに向きながらクチを開け笑っている。イタリア語などもってのほか。英語すらめちゃくちゃなのはしょうがないとして、やはりヘンなアジア人におもわれているだろうか? 困惑するわたしに向かって、おもいもよらぬ返事を投げてきた。
「マルコの家はすぐ近くさ。この店の並びに楽器屋があるけど、楽譜を探しに来たりするよ。“会いたいってことだよね”。え~と、電話番号はどこだっけか……”」
顧客帳かなにかをパラパラめくりはじめる。やがてその手が止まるとピポパッとプッシュし、受話器を耳に当てチャオとひと言、慣れた口調で話しはじめた。それから数分後、二度めのチャオを言ってプチッと電話が切られる。“一時間以内に来てくれるよ、よかったね(笑)”。
“!!!”ーー内心、期待はしていたものの、実際に来てもらうとなるとあまりの僭越に、かえってその場から逃げ出したくなってしまった。こともあろうに自分の父親ほどの人物を、それもイタリアを代表するピアニストを行き当たりばったりで呼びつけてしまったのだから。
“チャオ!”ーー約束の時間になると、こんどはドアが開く音といっしょに三度めとなるそのことばが店内に響く。レコード・ジャケットでさんざん見てきた人物が目の前に立っているではないか。もう笑うしかない。マルコ氏もほんわかした空気を醸しながら、体全体で笑っているよう。ボローニャという街の親和性を象徴するようで、イタリアを代表するジャズ・ピアニストには見えない。

彼のピアノはとても耽美ではあるのだけど、それを支える表現力には知的なフィーリングが絶え間なく流れている。こころの陰を描写するにあたって、演奏者がいわゆる“いい人”である必要はないというジャズの俗説は、マルコ氏と会い、やはり俗説にすぎないことがわかった。
ローマ、ミラノへ移動
居心地のいいボローニャはなんだかんだで五日間ほど滞在し、その後は南下しローマへ。街の玄関口テルミニ駅周辺には地元民と、クーフィーヤをあたまからすっぽりかぶった移民系であふれかえっていた。イタリアというより上野駅のそれをおもいだす。

テルミニ駅前
チェックインすると、まずは寝台のサイドテーブルの引き出しをごそごそとやり、ぶ厚い電話帳を確認。ほぼ手付かずなのは万国共通なのか。穴が開くほど目をくばり、レコード屋らしき店のページとにらめっこしながら明日からの作戦を立てる。
それでも勇み足を踏むような日がつづくとなると精神的にもしんどい。ローマにかぎらずイタリアのレコード屋はなかなかしょっぱかった。単純にモノがない、というのともちがう。そのこととどう関係しているのかわからないが、あることに気づく。まるで植民地か、というくらい、それなりの確率で日本盤が釣り上がるのだ。ロックもジャズもソウルもポップスもクラシックも。そしてこうした店は、プログレ寄りのロックが主流だったりすることが多い。レコード・クランケならここでピンくるはず。一部に人気のある日本盤は、トレード要員としてもそれなりに価値が高い。ご苦労なことに日本人の蒐集家がこの国に運びこんでいたのである。それも、けっこうむかしから。〈クアドロフェニア〉で告げられたことを想い出したーー“こんど来たときはジェイムス・ブラウンの日本盤を持ってきて。オビがついてるとなおいいんだけど……”。
最後は入国したときのミラノにもどるため、ボローニャをかすめるようにふたたび北に進路をとる。いま地図を開きながらこのキーを打っているが、ずいぶんめんどうなコースを辿っていたことに気づいた。

ドゥオーモ(ミラノ)
“イタリアまで来てヴェネツィアには行かないのか?”といったことも行く先先で言われた。しょせん観光モードではなかったあのときのわたしにそれは無理な注文だったが、いまならちがう。映画『旅情』のキャストみたくなって入り江を遊覧船でまわってみたい、そういうおもいのほうがつよい。
SHARE
Written by
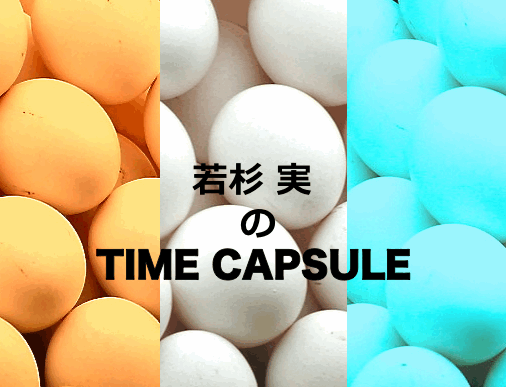
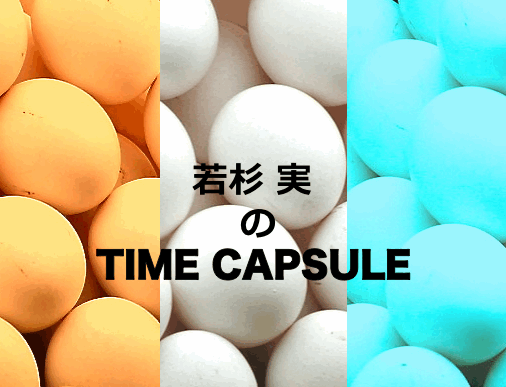
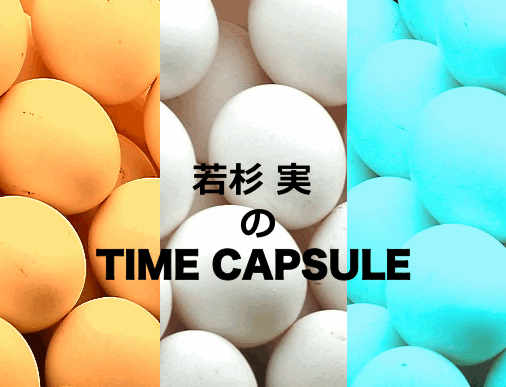
 若杉 実
若杉 実 