“フランス文化には甘口と辛口がある”とは、ほかでもないわたし個人の言だが、前回たっぷり辛口はつづったので、今回ばかりは甘美な旅情を。
その前回、フランスでの取材メニューに当時世界の音楽通を震撼させていたゴタン・プロジェクトのフィリップ・コーエン・ソラルに会うというのがあった。グループ名からもわかるように彼らの音楽性には、タンゴとそれにまつわるいろんな要素を現代のエレクトロニック・ミュージックに落とし込むというのがある。デビューアルバム『La Revancha Del Tango』(2001年)はインディーズからのリリースにも関わらず各国でトップセールを記録、全世界で百万枚を売りさばく。
この数年まえからわたしも、タンゴ、フォルクローレといったアルゼンチン音楽に食指を動かすようになった。こういう運命は過去にも例はある。めずらしいものではなかったが、このとき決定的にちがっていたこと、それは世紀末を目前とした奇妙な高揚感が、血の匂いがする音楽=タンゴと一体となってあらゆる物事の原動力となっていたことだ。
そうしたこともあって同時期、アルゼンチンをテーマにしたCD企画をドバッと片づける。最新の音源をDJミックスした『フォルクロニカ!』『〃2』から旧譜の編集盤『ブロンカ・ブエノスアイレス』といったものまで(以上2004年作品)。こういうものをまとめてつくろうとするパワーはいまないかもしれない。そうおもうと、すこし悲しくなるが。


フォルクローレという扉
当時のパワーの源泉はひとりのボンボ奏者ドミンゴ・クーラ(の音)との邂逅にあった。フォルクローレを代表する彼の作品、70年代のものだったが、レコード店でなんとなく手にして家に持ち帰りレコード針をおろした瞬間、目からウロコが落ちる。その針はどんなところでも、一定のリズムで刻むスネアを拾いあげる。ひたすら太鼓を打ち鳴らす、ある種、禅門のような世界であったが、こういうストイックな世界もフォルクローレにはあるのかと興をさかす。これまでフォルクローレといえば、駅前の広場で海外からの季節労働者がポンチョをかぶりやっているものだと信じていたから。
ゴタンに会うことになったとき、わたしの知識はあるていどいい感じに整えられていた。そうだったと信じたい。フィリップ・コーエンへの質問がそれによってまとまる。ようするにこういうことだろう。“あなたたちのやってることはタンゴの再構築だとか21世紀のピアソラだとかいろいろ指摘されていて、本音をいうとそういう質問は退屈、仕事を早く切り上げたいから適当に相づちを打ってきたけど、ほんとうは……”と、相手のこころを勝手に読みきったところで、核心部分に触れてみた。
「タンゴの影響ももちろんですが、それ以上にフォルクローレではないでしょうか。ドミンゴ・クーラをご存じですか? わたしの大好きな奏者ですが、ゴタンの作品からは彼の残像が浮かんで見えるときがある、とくに“La del Rus”という曲は……」
ゴタンの急所をつく
「……」ここで5秒くらいの無言が挟まれた直後、相好をくずすなり、コーエンのクチがおもむろに開く。
「まったくそのとおりだ。アルバムを出してからいままで世界中のジャーナリストがわたしと会話をしてきたけど、その名前を出してきたのはキミが初めてだよ。そして、その指摘はまちがっていない。これは初めて話すことになる。いいかい、ゴタンを立ち上げたのはドミンゴ・クーラがきっかけだった。彼の音楽に衝撃を受けて“これだ!”とおもったのさ」
このときのわたしはきっと、小鼻をピクピクとさせていたにちがいない。以上のようなこともあって帰国後、アルゼンチン企画にクーラのベスト盤をくわえることをディレクターに進言。コーエンからの推薦文も取りつけ完成させたのが『ドミンゴ・クーラ・アンソロジー』(2004年)だった。

後日譚。取材時にうかがっていたことだが、ゴタンの次作『Lunático』(2006年)にクーラを参加させるため、録音は現地ブエノスアイレスでおこなうという話を耳に入れる。取材の翌年、ゴタンのミックスCD『Inspiración – Espiración』(2004年)にクーラの古典「Percussion [Part1]」を選曲、伏線を張るようにリリースされたが、ここで予期せぬ事態がおこった。同年暮れ、クーラは演奏中に舞台で頓死してしまうのだ。そのためセカンドアルバムでは予定を変更、クーラへのオマージュも兼ね発表されることになった。
SHARE
Written by
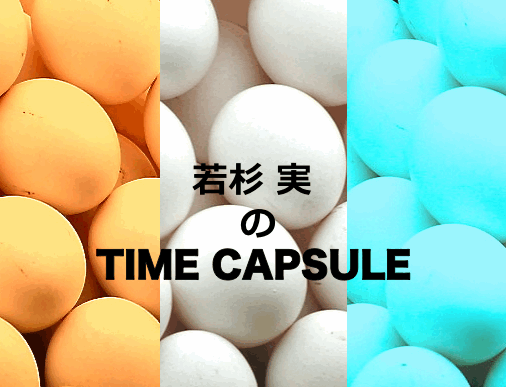
 若杉 実
若杉 実 