「模索していた」「自分の軸がわからなくなっていた」——およそ1年ぶりのシングルをリリースするDAOKOは、前作「ShibuyaK/さみしいかみさま」からの制作期間をそう語った。2015年3月、覆面女子高校生ラッパーという触れ込みで、ファースト・アルバム「DAOKO」をリリースし、華々しくメジャーデビューを果たしたDAOKO。作品はリスナーだけでなく、批評家からも大きな評判を呼び、アーティスト活動は順風満帆であるように傍目からは見えた。しかし、人知れず彼女は「自分の本当にやりたいこと」に悩んでいたという。もがきながらも、自らの求めるところを探し続けた1年弱……DAOKOが探し出した大切なもの、そして見据える未来について話を訊いた。
インタビュー・文=小田部 仁
私みたいな人間がポップスをやっているということで、誰かに勇気を与えることができたらいい
ーー今回、シングル「もしも僕らがGAMEの主役で / ダイスキ with TeddyLoid / BANG!」のリリースに先駆けて「BANG!」のMVが公開されましたが、これがリスナーの間で非常に話題を呼んでいます。曲調もヴィジュアルも前作からかなりラディカルに変わりましたよね。
前作から気がついたら結構、時間が経っていて。それだけにMVをご覧になった方々からは「DAOKOが変わった!」っていう反応もたくさん届いています。私としても「変わった」と思うし、「覚醒したな」と感じているんですけど……正直に言うと、私自身としては日々制作をしながらデイリーで自分の変化を実感していて。ずっと、蛹の中で蝶になる準備をしていた、っていう感じですかね。
ーーDAOKOさんはインディーズの時点からセルフ・プロデュースを意識的にやられている印象があって。この変化は何が原因でもたらされたものなのでしょうか?
心境の変化がありました。高校生の時から3年間インディーズでやってきて、メジャーの舞台に活動を移したわけですけど、自分の本当にやりたいことがわからなくなっちゃって。ずっと自分の中の軸が定まらずに、手探りで模索している状態だったんですね。「ShibuyaK/さみしいかみさま」で、自分の中ではDAOKOの第1フェーズが終わったという感覚があったので「さぁ、次はどういうアプローチでやってみようか」っていうことを、制作期間中、ずっと自問自答していました。
ーーこのシングルを作ったことによって、自分のやりたいことや軸が見つかったんでしょうか?
そうですね。自分の原点に立ち返ってみたときに、やっぱり音楽で救われたという経験があって。そもそも私みたいな全くポップじゃない、日陰を歩いてきた人間がメジャーのど真ん中でやっているということ自体が面白いことだな……と、思い当たって(笑)。私みたいな人間がポップスをやっているという事実が、誰かに勇気を与えることができたらいいなって。だからこそ、もっとDAOKOとして覚醒したい、変わりたいって思えるようになったんですよね。
ーー「BANG!」では楽曲の肝としてハンド・クラップがフィーチャーされていて、DAOKOさんのディスコグラフィーの中でも屈指のポップ・チューンになっていますね。Taylor Swiftの「Shake it off」に近いテイストもある。
これまでのライブでは私とお客さんの間にスクリーンを下ろして、映像を投影したりする演出方法を取り入れていて。お客さんとの距離を図りつつやってたんですけど。でも、ライブをお客さんも含めて体感するものに変えていきたいっていう思いがあったので、そこからハンド・クラップを使った曲を作ろうというアイディアが出てきました。
ーー「ShibuyaK」のMV監督も担当されていた児玉裕一監督が「BANG!」も撮影されていますね。青い婦人警官の制服に身を包んだDAOKOさんが拳銃を打ちまくり、外国人ダンサーと踊りまくるというかなりインパクトのある内容で。
今までと歌っていることはそんなに変わってないと思うんです。恋愛観と死生観を重ねてみたりしていて。ただ、表現の精度と角度が違う曲だと思うんですね。順接的ではなくて逆説的な方法論の方が刺さるんだろうなと思っています。
ーーあえて、イメージとして取り入れたという戦略的な企てが感じられました。
そうですね。今まで、アイドルとして見られることをすごく危惧していたんですけど。でも、マイケル・ジャクソンだって、言ってしまえばアイドルじゃないですか……? 好きなものって誰しもアイドル視するものなので。より多くの人に伝わればという感じでした。
ーーCygamesのCMソングにも使われている「もしも僕らがGAMEの主役で」では「僕らは誰? / 僕らは何して / 生きているんだろう?」という普遍的な悩みも歌詞の中に率直に描かれていますね。
カッコつけずに、模索してもがいている過程も見せていきたいなって気持ちがありました。それはポップ・アーティストを愛する理由の一つとしても美しいものだと思うし。これまでの作品は「悲しみ」や「怒り」みたいな感情を音楽にぶつけていたと思うんですよね。自分のために書いていたようなところがあって。毎日必死で他の人のことを考えている余裕なんてなかった。でも、メジャーで作品を発表するってことは広く人に聴いてもらえる可能性があるっていうことだから「これが私の考えるポップスなんです」というものを作りたかったんです。でも、完成ではなくてこれは過程の段階だと思っています。TeddyLoidさんと作った「ダイスキ with TeddyLoid」なんかはテイストが強いし。
SHARE
Written by



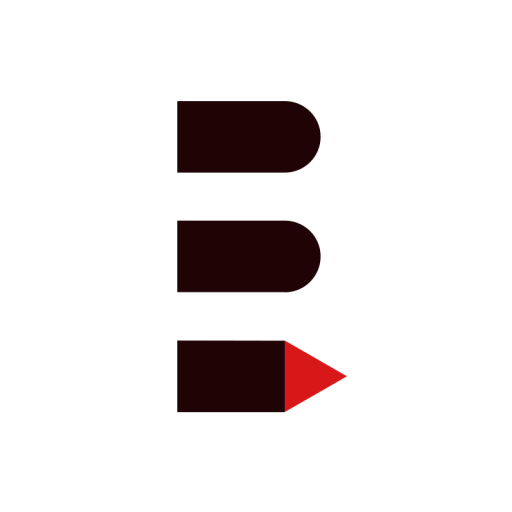 MEETIA編集部
MEETIA編集部 