5回にしてようやく90年代。長い道のりだった。この間いろいろあり、詳細は割愛するけど、その前半、傾倒することになったのがブラジル音楽。だから、こちらも道のりは長い。
なにしろ海外は初めて。片道28時間(外国だから)。3回のトランジット(地球の真裏だから)。夕食→朝食→夕食→夕食→昼食……という不順な機内食(こんなに食べていいんだ!→もう飽きた)。荷物が迷子(南米だから)。どれもこれも“ブラジルだから”と、じぶんに言い聞かせることで納得するほかなかった。
初めての企画
1994年に〈ニュー・バランソ〉というブラジル音楽の企画を監修する。1960年代のボサノヴァの代名詞エレンコ・レーベルの名盤を中心としたアナログレコードの再発。発売元がマンハッタンレコード(渋谷)の母体だったレキシントン社(現在は別会社)。最初にプレゼンしたのが系列のジャズ専門店だったこともあり、現地での買いつけも提案。夢のブラジル行きがこれにて実現した。

*企画のパンフ。名前はもちろん例のスニーカーをもじったもの。“あらたなグルーヴ(≒バランソ)”とかそんな意味。1994年の春から夏まで、4回にわけてリリース。エレンコ以外は独自のコンピなど。知らないうちにビームスが協賛になってた(苦笑)。
最初の海外がブラジルだったというのもあれだが、門前の小僧の企画をあっさりと受けいれてくれたことに、いまもっておどろくほかない。よくいえば寛大、そうでなければ……!? 社風がそうだったし、それ以前に時代がそういうものだったのかもしれない。学生生活を終え定職に就かず、いろいろやるなか闇夜に提灯、この業界とは無縁だったのに、これだけの大役をまかせてくれたのだから。どれだけ感謝してもしきれない。関係者のみなさま、オブリガード。
むかった先はサンパウロとリオ。本命はバイーアとかマナウスなのだろうが、ビギナーごときが生意気いっちゃいけない。人生はまだ長い、次回におあずけ……(といって行けてないが)。

サンパウロの空港に降り立つ。その瞬間、巨大なサウナの中にでも放りこまれたような、むせかえるような熱に全身がつつまれ、とっさに胸元をゆるめる。そこで待機していた現地のコーディネーターと、あいさつ代わりのエスプレッソをその場でゴクリ。舌をピリリと刺激する本場の苦味が気つけとなり、「よし、当面日本人として生きるのはおさらばだ」と、よくわからない決心をしたのだった。
それから先は、エスプレッソよりも濃厚で甘美な毎日が。目に焼きつくのは、なにもかも新鮮なものばかり。うつくしいものも、そうでないものもどちらも混在している現実に、南米随一の大都市の真理を読んだ気になる。そしてこう想いをはせる。日本とりわけ東京に足りないもの、それは飢えにたいする自覚ではないか。帰国して渋谷にもどり、いつものように歩いていると、ふと嗅覚が鈍感になっているようにおもえた。「鼻をつまんでいるような街だ」――しばらくはそんなことをかんがえさせられたり……。

*なによりいちばんの心配が治安。観光客にみられないようにと、街中でのカメラは極力ひかえることに。そのなかで撮った一枚。

*それでも観光地へは行く。コルコバードの丘(リオ)より、キリスト像は背中で語る。尺は高崎観音とほぼおなじ。
音の神秘
ブラジルにはリズムがあふれている。月並みすぎるが事実だ。しかしブラジルは、そのリズムをこわれた蛇口のようにただ流しっぱなしにしているだけではない。街中に溶けこみ、路地裏へと吸いこまれ、行き交うひとたち、走り去る若者たちの肉体に宿され、やがてどこかに、音楽なら音楽に、サッカーならサッカーに、アートならアートにと、円環を描くように有機的に運動させている。
リズム(鼓動)は音楽だけに限定されることもない。意外というか、サンパウロもリオも街中を歩いたところで、どこもかしこも音楽であふれかえっている、というのともちがっていた。先般のリオ五輪を目前に失速した、つかの間のバブル。その助走期間だった当時、外資系企業、大型CDショップの看板が景観に、ぽつぽつとまじわりはじめたように、色めきたつ空気や熱のようなもののほうがむしろ敏感にキャッチできた。
それでも、音楽のない人生などありえない、という国民のエネルギーが、この街で行き場を見失うなんてこともない。陽が沈み、夕飯後に投宿先の近所を散歩していたときのこと。気持ちいい夜風があたる中、ギターの弾き語りが小窓をまたいで路肩までこぼれてくる。やさしい音がしっぽりと、しかしはっきりと聞こえてくるのは、街によけいな音も灯もないからだろう。しかし、そのよけいなものがなんであるのか、日本にいないとわからない。
アーティストに会う。そしてレコード屋へ
エドゥ・ロボとホベルト・メネスカルに会う。企画の中に彼らの作品がふくまれていたからだ。媒体向けの取材も兼ね、当時の話を聞いた。メネスカルは温厚だが、ロボはすこし気むずかしいインテリ系。そのロボのとき、コーディネイター(彼も音楽家)がいじわるなちょっかいをだす――「ライザ・ミネリとの逢瀬はどうなったかおしえてもらいなよ」。これがどれほどの意味をもつのか、このときはよくわからず。おわり際におずおずとたずねてみると、ロボの顔色がほのかに変わっていくのがわかった。
メインとなる重要な仕事。仕事が仕事なので、手当たりしだいレコード屋(おもに中古屋)をみてまわる。おもえば“レコード屋をまわる”というのが“習慣”ではなく“仕事”となったのは、このときが初めて。気兼ねする必要がないという贅を、地球の真裏まで来てあじわえるとはかんがえてもみなかった。
“レコード屋をまわる”というのは“レコード屋に行く”のとも微妙に……というかまったくちがう。前者についてまわるのは、うしろめたいという感情だ。“お宝探し”という大義名分のもと、懐の寒さをまぎらわしているだけだったりする。食事の時間さえ惜しむように。飢えの自覚ってこういうことだったのか!?

*レーベルも運営している有名なレコード屋〈MOTO DISCOS〉の制服(サッカーシャツ)。まとめて買えば値引き交渉はあたりまえ。それも物足りなくなり、せしめてきた。店はもうなくなってしまったみたい。
当時、ブラジル音楽のトレンドはロンドンのクラブから発信されていた。彼らが対象とするのは一般的な歴史、系譜から外れたもの。コアなジャズだったりファンク系だったり、マイナーなMPB(SSW系)だったり(ようするに現在では定番になっているもの)。現地ではまだプレミアがつけられていなかったとはいえ、そういう代物と遭遇する確率はめっぽう低い。あればあったで、“値札の貼りまちがえ!?”とおもえるようなものだったりするのだけど。それに、エレンコの原盤にいたっては、そうした心配がいらないほど。それこそ、このときの企画の意義を自問してしまったくらい。「わざわざ再発しなくても、このままごっそりと買いつけてくれば事足りるのではないか……」
“ボサノヴァは演歌みたいなもの”とは、よくいわれること。想像するまでもなく、日本でのあつかわれかたとそれはおなじ。もちろん演歌は日本の宝だし、ボサノヴァもそういうことになるが。
やがてネットの時代に、情報が世界で共有されるようになり、いまは閉鎖してしまったがGEMMのような巨大マーケットが誕生し、ebayのような世界のオークションサイトが大手をふることで、いっきに青天井となる。そりゃ現地のディーラーが“レコード御殿”をぽんぽんと建てちゃう(実話)わけだ(つづく)。
SHARE
Written by
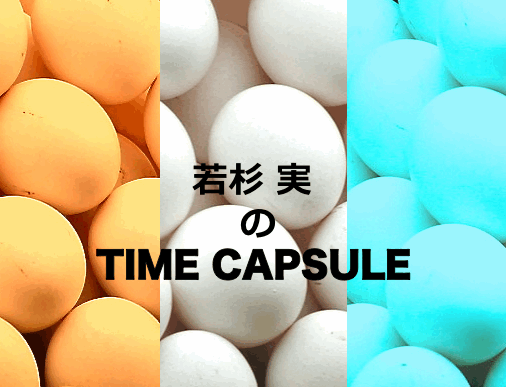

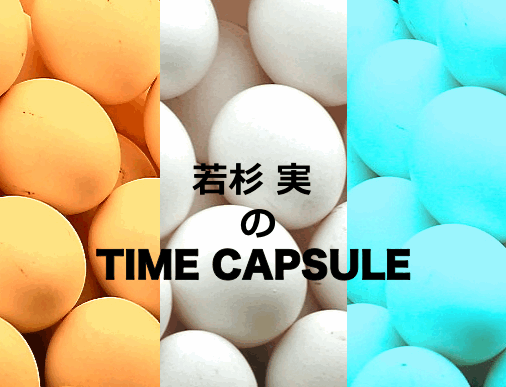
 若杉 実
若杉 実 