1.5回め(?)のフランス
2003年師走、雑誌の取材でパリとロンドン(次号)をおとずれる。ロンドンはこの時点で三度めだったが、パリはシャルル・ド・ゴール空港で一夜を明かしただけ。街の空気は吸っていない。
フランス人はなにかとめんどうな国民といわれている。仲良くできるのならそれに越したことはないのだろうが、とんだ災難のおかげで、どうやら相性のよくない関係になってしまったらしい。
それでも支度をしているあいだに過去の悪夢もすっかり忘れてしまっていた。エッフェル塔、凱旋門、サンジェルマンデプレ、パリジェンヌ……観光ガイドで目にしてきた絵が、“オ〜・シャンゼリゼ♪”に乗ってあたまの中を旋回する。
各都市一週間ずつのスケジュール。仏英にちなんだジャズ総特集ということで、このときばかりは時間に余裕がない。新旧世代をまんべんなく取材。アンリ・サルヴァドールのような傘寿過ぎも対象にふくまれていた。じつはこの4年後に亡くなられてしまう。取材も30分ほどで短めに切り上げたが、生前お会いできたことに感謝したい。
そして彼だけではない、貴重な体験の数々が列をつくって待っている。渡航まえ編集者と打ち合わせをしたとき取材リストをつくった。ようするに“あのひとに会いたい”リストである。ストーリーを組み立てつつ、そこに適したアーティストや店などを割り振る。おのずとそこには大御所、名店の文字がならぶ。
アンリをはじめミシェル・ポルタル、フランソワ・テュスク、ゴタン・プロジェクト(次回)、それにパリス・ジャズ・コーナーといった地元のレコード屋なども。アンリもそうだったが、クレモンティーヌやフーディング(レストラン・ミーツ・DJカルチャーみたいなもの)と呼ばれていた最新のナイトスポットなどが編集部から提案された。雑誌がモード系だったこともあり、そういう絵も外せない。それにつけてもわたしは、ずいぶんシブいところをあげていたんだなぁ。
ジュウタンに地図をつくる
そのクレモンティーヌのところでやらかしてしまう。不吉な予兆はあった。向かう途中、ダイアナ元妃が事故死したアルマ橋下のトンネルをくぐったとき、一瞬、胸中がざわつく。出向いた先は別宅のような場所だったと記憶している。両家のお嬢さんらしく両親といっしょに待ってくれていた。「まいったなぁ、母ちゃんまでの質問は用意してないんだけど……」。
部屋を飾る調度品は高級そうなのに嫌味がない。たぶん、ほんとうの金持ちってこういうことなんだろう。家族のワードローブをガバッと開けると、やっぱり10着ずつしか服がなかったりして。品のある部屋の空気が鼻腔をくすぐる。緊張するどころか、ヘンにくつろげる。しかし、かえってこれがいけなかった。
持参した録音機の電源を入れてから40分が経過。家族と談笑しているような時間がつづく。「もうそろそろで本題に……(汗)」とおもってた矢先に絶妙な間の手が入るーー「さあ、ワインでもいただきましょうよ」。
窓の外はまだ明るい。下戸ではないが上戸でもないわたしは二杯めが注がれたとき、グラスをもつ手がふらつきジュウタンの表面にこぼしてしまった。直径30センチほどに変色した跡はいまでも残っているだろうか。どうせなら、よこにサインでもしておけばよかったかな。
憧れの音楽家と対面
フリージャズの“フリー”とは、もちろんアルコールフリーの“フリー”ではない。むしろ度数高めのアルコール、テキーラのショット飲みみたいなジャズのことをいう。クレモンティーヌ家は代々そうしたミュージシャンを多数サポートしてきた。ようはパトロンである。ワインで地図をつくってしまったジュウタンが敷かれたあの部屋ではむかし、彼らを集めて毎日のように演奏会をやっていたのだとか。
そこでも“まずは一献”といって、みんなを振る舞う。夜もふけるころにはすっかりできあがっているから演奏どころではない。「この窓からベースを担ぎ放り投げた者もいたぞ、ワッツハッハ……」と、シャツのボタンがちぎれそうなお腹をなでながらクレモンティーヌのパパがのけぞる。なるほど、ジュウタンどころの話じゃない、ホッとそこで息をついた。
このあと取材したフランソワ・テュスクにその話をしてみると、大笑いしながら放り投げた人物の名前を想い出してくれた(が失念)。そもそもアルコールだけで上気していたのかもいぶかしいが。ともあれあの時代、映画『パリは燃えているか』(1966年)よろしく、いろんなものがくすぶり荒れていたことは想像にかたくない。
テュスクのデビュー作にして問題作、その名も『Free Jazz』は『パリは燃えているか』の前年(1965年)に発表された。そのまんまのタイトルどおり国内初のフリージャズ(作品)とも誉れ高い。このアルバムを最初に聴いたときの衝撃はいまでも忘れられない。CD化されてからまもないころだったため、長年聴いてみたい願望がそこで叶った。
ふしぎなことに、わたしは寝るまえ照明を落とし布団にくるまって聴く習慣があった。そのまま夢の中に入ってしまうことはなかったが、あたまの中が整理され妙にスッキリする。複雑に絡む楽器同士が血管に入ってきれいに掃除をしてくれるかんじ、といえばよいのか。バスクラを中心とした管同士の対立に絶妙な空間性が帯びる(対位法というやつか)。セラピー効果のあるフリー系というのもヘンだが、それほどわたしの肌には合っていた。
国民性はこむずかしくても、この作品には理解と愛情を深められる。それほど入れ込んでいたアーティストを目のまえに、終始、身体が白昼夢のような時間につつまれる。「わたしを取材した日本人はキミが初めてだよ」とまでいわれてしまうと、(自慢しているようでヤだけど)やっぱり記者冥利につきるというもの。サインをいただこうと、貴重な原盤をしっかり梱包して日本からもってきたかいがあった(こういうことはめったにしないのだが)。
『Free Jazz』でバスクラを吹いていたミシェル・ポルタルにこのあと取材。若気の至りでジャズロックをやっているデビュー作『Our Meanings And Our Feelings』(1969年)のこと(画像/動画は別の作品)、例のベースを投げた奴はだれか、の話まではよかったものの、テュスクとやっていたことに話題が切り替わるとポルタルの目が一瞬すわる。ジャズってそういうところがむずかしい。

SHARE
Written by
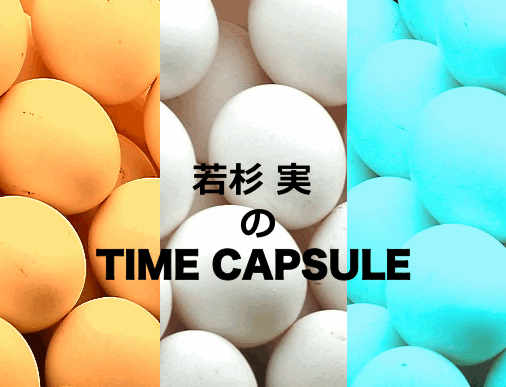
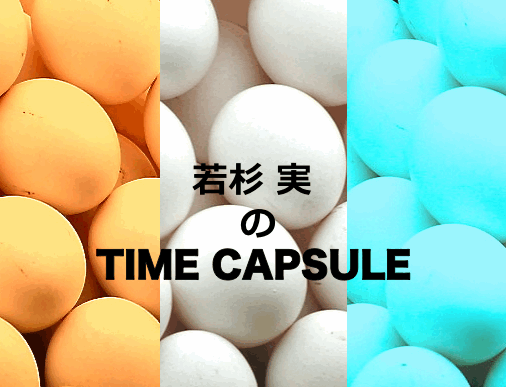
 若杉 実
若杉 実 