(前回のつづき)
じぶんの目ん玉をうたがった。信じられない光景が指呼の間にひろがっていた。電流をクチから飲みこむように身体の内側から全身の皮膚をビリビリとふるわせている。彼の名前はマイケル“ブガルー・シュリンプ”チェンバース。映画『ブレイクダンス』で準主役を張る人間にまちがいなかった。
なんというぐうぜん。“本日、代々木公園ホコ天に出没!”と、ツイートできるような時代の話ではない。どうやら新作『ブレイクダンス~ブーガルビートでTKO』(『ブレイクダンス』の続編の邦題)のプロモーションで来日していたらしい。夕刻、そのあいまに日本の有志たちがあつまる聖地に立ちより、本物のポッピン(パントマイムの進化形)をみせてやろうというところで、群衆のひとりに田舎の坊主がいた、ということになるのか。シュリンプが羽織るナイキのウィンドランナーが小刻みにゆれて、虫の羽みたいな音をだす。いまでも耳元に呼びもどせるほど、彼との距離はほとんどなかった。
MJの専任講師
マイケル・ジャクソンの“パーソナル・ポッピン・インストラクター”だった――そうした肩書きをふくむ、シュリンプにまつわる逸話はそれなりの時間が経過しないとオープンにはされなかった。マイケルのステージやPVをふりかえると、『ブレイクダンス』で披露されたポッピンの数々が、多少のアレンジをくわえ再現されているのがわかる。つまりそれは、“シュリンプのもの”として受けつがれていたことを意味する。マイケルの逝去後、せきを切ったようにシュリンプの証言が拡散されるが、ビジネスパートナーとまではみとめられていなかったかもしれない若きストリートダンサーの暗部すら、そこににじんでみえるのは気のせいだろうか。その“ポッピンの数々”の集大成として、『ブレイクダンス』のある場面、通称“ターボ(シュリンプの役名)の掃除”をおもいだすひとは、今日ビジネスとして成就したストリートダンス業界のなかにおおい。シュリンプ扮するターボがバイトする食料品店のまえで、掃除と称しポッピンを舞う。ごみを掃くようにしながら手にしたホウキが小道具として効果的につかわれる、劇中、白眉のワンシーン。その絵はだれもがまねしたくなるものだから、とうぜんじぶんもまねをした。現在のアニメーション(・ダンス)の鼻祖といっていい。
この場面には、ポッピンにまつわるあらゆる可能性、サジェスチョンが詰めこまれている。なかでも注目すべきはバックスライドの特異性について。今日ムーンウォークと呼ばれるそれは、ここにかぎってスライドの幅がおおめにとられている。また、これと連動して、通常では軸足を足指で支えるのにたいし、シュリンプは足指→つま先とそこにもう一枚噛ますことで、うしろへの流れ+フロートのような浮きあがる動作を加味させている。165センチという短身だったハンデをダイナミックにみせるためだったらしい。
さらに、ミュージカル映画にくわしいひとなら、ここで指をパチンと鳴らすはず。往年のフレッド・アステアが『恋愛準決勝戦』(1951年)のなかで、コートハンガーを相手に踊る場面(動画前半)を彷彿させるからだ。続編『ブレイクダンス2』になると、部屋の床→壁→天井をつたって踊る無重力の舞ともいえるトリッキーなひと幕があるが、これとまったくおなじ撮影技法(動画後半)は『恋愛準決勝戦』のなかにもある。アステアへのオマージュにちがいないだろうが、シュリンプのようなストリート系にすら影響力をもつダンスの神の偉大さを痛感せざるをえない。
ラジオのヴォリュームを上げるとき
話を音楽に切りかえる。先般、上梓した『裏ブルーノート』の刊行記念で、ブロードキャスターのピーター・バラカンさんとトークイベントをさせていただいた。たまたまだが、『ブレイクダンス』の日本版パンフレットの解説は、若かりし日のバラカンさんが健筆をふるっている。
これは意外というか発見だろう。80年代に〈ザ・ポッパーズMTV〉(参考動画)の司会をやられていたものの、じつは番組であつかった音楽はそれほど……!? という裏話もあるくらいだから。
この件に触れることはなかったが、これとはべつにトークでは音楽に開眼した契機がラジオだったという共通の話がもちあがり、当時を回顧するうちに感慨深くなってしまった。テーマだったジャズについてだが、じぶんも高校時分、夢中になったラジオから流れてきたケニー・バレルの「Midnight Blue」を、耳が初めて“これがジャズか”と認識したのをおぼえている。その筋では伝説とされるFM東京の〈FMトランスミッションバリケード〉という番組で、土曜の27時、つまり日曜3時からの1時間にかかる音楽はクラブ系。主流だったヒップホップがいちばんおおく、そこにあらたな波として浮上していたユーロビートやハウス、のこりはニューウェイヴやレゲエ、ワールド、サントラという順で、その合間を縫うようにジャズが挿入されていた。
“いつラジオのヴォリュームを上げたか”――ラジオによる音楽体験をいつもの乾いた文体で、片岡義男は自著『ぼくはプレスリーが大好き』のあるチャプターにそう記す。“ポップミュージックの本質をつく一文である”と村上龍が共鳴、指摘していたことで知ったが、わたしもそのとおりだと、深く同意したい。自発的に音楽を聴く態勢が整えられたことを告げる、淡い青春の一ページ。
アンテナ、睡魔と挌闘
もっとも、音量のつまみではなく、手前はアンテナと挌闘していたから、たいして色気のある話にはならない。ラジカセの背に手をまわしてスルスルッとその棒を伸ばし、窓を開け、都がある方角に先端をむけながら電波の通り道をさがす。はぁ~、おなじ関東圏でも北関東(地元)は別天地なんだなぁと、ちいさなため息をそこで吐く。深夜帯でもクリアな音は長くつづかず。大型トラックが軒端をかすめようものなら無線で妨害される。窓枠に切りとられた満天の星は、そんなときでさえ味方にはなってくれない。睡魔とも挌闘しながらエアチェックをし、FM情報誌の番組表と突きあわせ曲を目で追っていく。それでも変更、記載漏れとかはあたりまえだから後日、局の窓口まで問いあわせる。そんな電話しないでちょうだい、仕事だから受話器をとってるのよ坊や、と、本音を押しころしながら事務的に応対する受付のおねえさんは、調べますのでかけなおしていただけますか、と作り笑いが透けてみえるような語調でこたえるが、これ以上わかったためしがないため、毎回あきらめる。
ただし、そのあきらめた音源を、もういちどだけ救済してやる方法をかんがえ実行にうつす。再度、編集しなおした一本のカセットテープを、東上するときある場所に持ちこむ。六本木交差点にありながらも隠れ処のようにたたずむ、いつ倒れてもおかしくない雑居ビル。そこの三階まであがり、さらに奥のつきあたりまで歩いていくと、蛍光灯の束から陽気な音がもれてきた……(つづく)。
SHARE
Written by


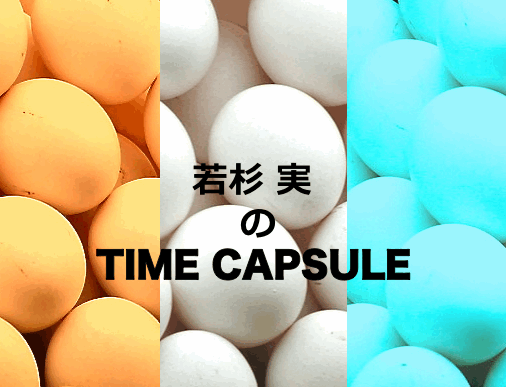
 若杉 実
若杉 実 