“DJ=ディスクジョッキー”といえば、ラジオでおしゃべりしながら音楽を紹介するひとのこと。一般的な解釈として、この説明はまったくもってまちがいではない。しかし、これまで触れてきたこと、あるいはMEETIAであつかうDJの意味としてはそれなりの違和感が生じやすい。80年代後半になれば、すくなくともラジオとは切りはなされ、単体として存在することが世間でもみとめられるようになる。
レコードをあつかいお客を踊らすDJはディスコ黎明期から存在したが、80年代になるとレコードに直接手を触れ、前後にコスるなどしながら楽器のように音をだすスクラッチという手法がにわかに浮上する(参考動画はスクラッチのドキュメンタリー映画のトレーラー)。これがひろく浸透すると、DJたちのあいだに技術を磨く者があらわれ、やがてショーアップされたものへと昇華。たがいの技術を見せあい競いあう競技会DJバトルにまで発展する。
日本初のDJバトル大会
冠大会では国内初となる〈ベスタクス~オールジャパンオープンDJバトル〉が開催されたのが、1987年11月15日。主催者ベスタクスは日本の音響機器メーカー。惜しむらくは2014年に倒産してしまったが、その品質をもってディスコ黎明期からディスコミキサーの定番として世界で高いシェアをほこっていた。

こっそり応募する
これにともない、数ヶ月まえからカセットテープによる予選審査がはじまる。この情報をどこからともなく聞きつけると、部屋にこもってせっせとテープづくりに励んだ。じぶんなりにテーマを決め、どうせならばと二本立てとすることに。一本めをヒップホップにしたのはとうぜんとして、もうひとつはなににしようか?……そうかんがえあぐねていたとき、こんな情報を小耳にはさむ——「ハウスという音楽がキテるらしい」。もっとも、まだ田舎で学生をしていた時分、その“家”の実態がなかなかつかめない。唯一知らされたことといえば、「速めのリズムにジャズっぽいピアノがサンプリングされている」というもの。あとあとこれが、あまりにアバウトすぎる説明だったことを知るが、山っけよろしく善は急げと適当に解釈し、ハウス風にすらなっていない、勘違いな曲をミックス。四つ打ちもどきのラテンフリースタイルのBPMを、ピッチコントローラーをつかってプラス5くらいまで強引にあげ、そこにジャズだったかフュージョンだったかのピアノソロをかぶせるというものを、“わたしのかんがえるハウス”としてテープにおさめ、ベスタクス宛てに郵送した。結果はいうまでもなく……後日、参加賞とともに決勝大会の入場整理券がはいった封筒がとどく。

*各種アイロンプリント。つかえなかった……はずかしくて。
開催場所は新宿南口、甲州街道付近にあった〈サンスイ〉(こちらも2014年破産の音響機器メーカー)のショールーム。蛍光灯がまぶしい無機質な空間のなか、正面奥のDJセットは二台をよこならびにした会議用テーブルのうえ。客席も、プロレスの場外でよく放り投げられる、頑丈なだけがとりえの折りたたみイス。つまり、ランDMC、ビースティ・ボーイズ、パブリック・エナミーと、ラップ界の大物がたてつづけに来日(前回参照)していたにもかかわらず、現場では追いついていないところが多々あったということになる。
内容もそれに負けじと、かなり雑多、ある意味ぶっとんだものをみせられる。のちに寺田創一と手を組む、当時高校生だった現ナイトペイジャー代表・横田信一郎(優秀賞)や、元コンプリートフィネスのディレクターだったDJ IZUこと泉谷隆(準優勝)のようなセミプロもエントリーしてはいたが、そんな玄人はだしを差しおくように印象づけていたのは、むしろ“追いついていなかった!?”ひとたちだったのかもしれない。

*出演者リスト
大学のDJ研究会が架空のラジオ番組を“オンエア”するわ、レコードをBGMにギターをかき鳴らすロックなお兄さんがスタンドプレイをするわのテンヤワンヤ。「それはちがうだろ……」と顔色にはでているものの、「まぁ初回だから……」と、コンセンサスをとりつけているような空気が会場をやんわりとつつむ。
ふたつの“石”
そんな生ぬるさに稲妻を走らせるがごとく場内を一変させたのが、優勝候補のひとりだったDJクラッシュこと本名、石英明(エントリー名)。「みんなが待ってたのはこれだろ?」といわんばかりの王道たるコスりを連射。DJジャジー・ジェフ&フレッシュ・プリンスの「The Magnificent Jazzy Jeff」(参考動画)を2枚づかいし、当時にして最新技だったトランスフォーマースクラッチを中段でかましながら、最後にそのレコードをかち割るという荒技で会場を色めきたたせた。
これで、優勝者としてアナウンスされるべき人物は決まったもどうぜん。そうだれもが確信していたところに、審査員席に座る高木完、藤原ヒロシほか(失念)が読みあげたのは、おなじ“石”でも“石田(義則)”のほう――「27才、レゲエのリズムにのせて、何をいっているのか分かるテンポのラップ、やはりアブナイ会社員」(出演者リストのプロフィールより)ことECDの名が、この瞬間ひろく知れわたることになる。
まさに、とんびに油揚げ。「DJコンテストなのに……!?」――一瞬、天井の蛍光灯が間引きされたかのように暗雲がただよう。出来レースとの憶測も飛びかっていたが、しかし結果的にジャッジはまちがっていなかったのかもしれない。「何をいっているのか分かる」日本語ラップは、たしかに新鮮というか、個人的には初めて。たいし、DJのスキルにはオリジナリティが不足、発展の余地あり、との審査評だったと解釈してやれば話は腹におちる。
当時ならやむをえないことだったが、本場USの右へならえだった日本のDJ界に一石ならぬ“二石”も投じられるなか、国内初のDJバトルは幕を閉じたのだった。
SHARE
Written by
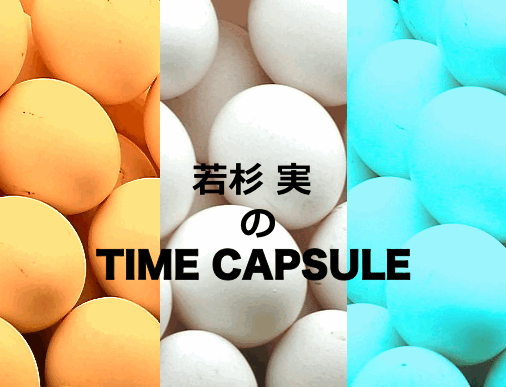

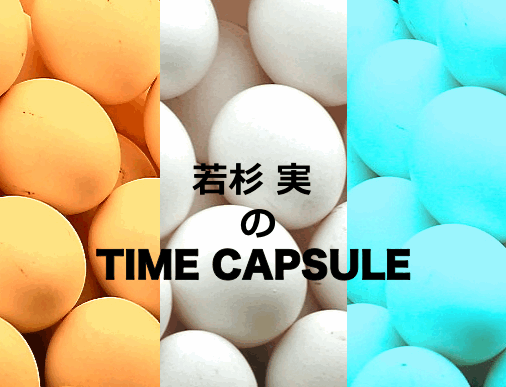
 若杉 実
若杉 実 