5月16日、第30回三島由紀夫賞の選考会が行われ、宮内悠介『カブールの園』の受賞が発表されました。宮内悠介が三島賞候補になったのは今回初めて。同作は雑誌『文學界』に掲載された際に第156回芥川龍之介賞にノミネートされていましたが、惜しくも落選。宮内氏は昨年、三島賞と同日に選考会が行われる山本周五郎賞候補にノミネートされていました。

第30回三島賞受賞作・宮内悠介『カブールの園』
「非常に感銘を受けました」選考委員・平野啓一郎が語った受賞理由
受賞作発表は選考委員のひとりである平野啓一郎氏が行いました。平野氏は代表選評で受賞理由について、「一選考委員、一読者として非常に感銘を受けました」とした上で、次のように語りました。
『カブールの園』は3世の問題。1世、2世のように強烈な体験が就職とか、結婚のたびにくるわけではなく、もっと複雑な形で差別の問題が日常の中にある。物語の中心では母親の関係が描かれていて、差別の問題は否認され続けているけれど、探って行くと個人的な問題を超えた背景に自分が経験してきた差別の問題に突き当たらざるを得ない。その社会と自分の折り合いの中で、実感とアイデンティティの分裂の問題がVRを使ったり音楽のミキシングのアプリなどのガジェットを使いながら、フェイク(二次創作的な世界)と現実(オリジナル)という仕掛けを使ったりなど、非常に巧みに描かれていて、それが作者のポテンシャルと作品の完成度がいいバランスで調和していたと思います。
実は評価が高かったのは『半地下』という収録作。現実と虚構との、日本人としてアメリカに住んでいる二重性をプロレスという、どこまでが虚構でどこまでが現実か分からない、しかも僕たちが知っているものとはちょっと一線を超えたようなアメリカの、日常とショーがどこまでなのか分からないような、ある意味での現実の馬鹿馬鹿しさが巧みに織り交ぜられていました。また、日本語と英語というふたつの言語の狭間で生きている登場人物の実感と苦悩というものが巧みに描かれていて、受賞に至りました。
第30回三島由紀夫賞は宮内悠介さんの『カブールの園』に決まりました。僕のイチオシ作品だったので、嬉しいです。おめでとうございます。詳しくは来月の『新潮』の選評で!
— 平野啓一郎 (@hiranok) May 16, 2017
宮内悠介が語った三島賞への想い
平野氏の代表選評後、若干緊張した面持ちで会見に姿を見せた宮内氏は、三島賞受賞に対してまず読者と選考委員に感謝を述べたあと、次のように想いを語りました。
三島賞の候補にしていただけただけで宝くじに当たったようなもの。それが更にいただけで恐れ入るばかりです。『カブールの園』の表題作はアメリカの日系人を扱ったものです。だから、今回真に受賞したのはもしかしたら彼ら日系人かも知れないなという思いはあります。ですからあたかも虚空に賞が与えられたような、若干奇妙な気持ちでいます。
『カブールの園』で第30回三島由紀夫賞をいただきました。一番ご報告したい相手は、作中で取り上げた、アメリカで細々と日本語の文芸活動をしていた日系人たちかもしれません。あなたたちの物語が、三島賞をとったのですと。そして、応援してくださいました皆様にも! どうもありがとうございます。
— 宮内悠介 (@chocolatechnica) May 16, 2017
他候補作の選評
平野氏は代表選評で、全候補作について触れていました。
『リリース』古谷田奈月

出典:光文社HP
文体の密度を評価する声もあり、これだけの分量を描き切ったということに対して、この作品を一番に推すという選考委員もいました。その反面、バランスが悪い、文章に難がある、5章以降が破綻しているという点で読みづらかったという否定的な意見もありました。また、作品としてもう少し編集的に整理されてある水準の作品に仕上がっていればよかったけどこの完成度という点で物足りないんじゃないかという声もありました。作品のポテンシャルを評価する声もあったものの、最終的には受賞作としての票は集まりませんでした。
『青が破れる』町屋良平
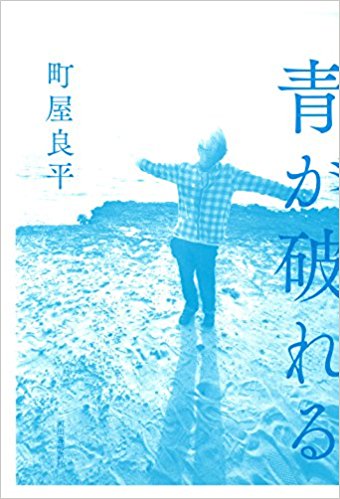
出典:河出書房新社HP
ひとりの選考委員が受賞作にふさわしいんじゃないかと推しました。文章、文体が醸し出すこの作者独特の雰囲気、リリカルな世界、それを評価する声、春夏秋冬の名前に関した登場人物たちと四季の移り変わりで起きる人間の生死の描き方を巧みだと評価する声もある一方、現代性といったときに、この作品が今書かれることの必然という点で社会性が欠落していて自意識のみで構成された世界ではないかという意見もありました。ただ、この作品自体は好評価だったものの、収録されたほかの2作の評価が全体的に低く、この2作がなければ受賞作に推したかったという声もありました。
『ビニール傘』岸政彦

出典:新潮社HP
聞き書きのような形でいくつかのエピソードが羅列されていて、そのつなぎ目にある種の文学性が書き表されるべきではあるが、それがある議論を基にしたまとめ方になっていて、文学作品としてどうかという意見がありました。僕自身はこの作品は今の社会が見るべき現実を捉えていると思いましたが、読んでいくうちに作者のまなざしに共感できないところがありました。小説はある意味では相手の心をすべて書き切ることができる。だからこそ最後の最後には他者として分かり切れないところをどういう風に丁寧に描くのか、という問題があります。作者は自分のことのように共感を強く持つのかというのが大事になってくる気がするが、この作品ではそれが逆になっていた。それをリアリズムとして評価する見方もあるが、結局読者がこれを読んだときにどういうことを感じ取るべきかということを考えたときに、この人たちがこういう状況に陥っていることを、社会的な問題と言うよりも属人的な問題、この人たちの問題という風に見えてしまう。そこに、小説としてのまなざしとしてはどうなのかなと疑問がありました。
『スイミングスクール』高橋弘希

出典:新潮社HP
エモ系と評した選考委員もいましたが、非常になんとなく物悲しいようなシチュエーション、出来事が淡々と綴られていく。それが好きな人もいればそうでない人もいる。そういう否定的な評価がありました。その淡々とする中に、何も起きないけど何か起きそうな感じがあってよかったという意見もありました。僕自身は強く否定する理由もありませんでしたが、同じように毒になる母親がいた作品としてしては『カブールの園』の方が芸があり、相対的にこちらが劣ると思いました。起伏の無い淡々とした描き方にある種の物足りなさがあり、女性の視点で書かれているがその視点、人称の選択に否定的な意見もありました。
来月発売される『新潮』7月号には詳しい選評が掲載される予定です。文学ファンは是非チェックしてみてください。
Text_ Michiro Fukuda
SHARE
Written by
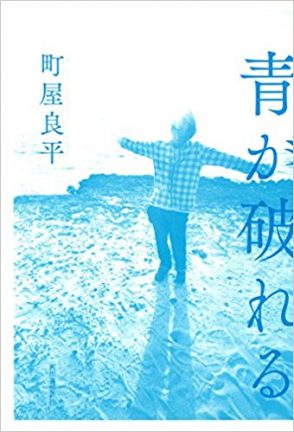

 山田宗太朗
山田宗太朗 